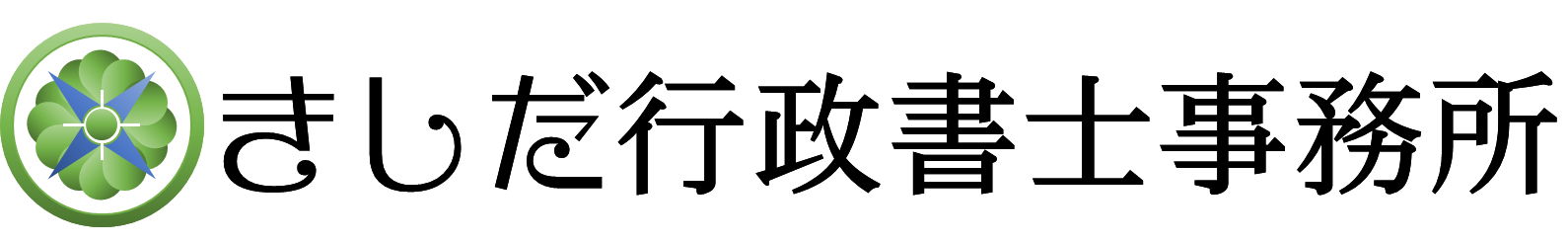【グループホーム(共同生活援助)指定基準】基本となる基準について
神戸三宮で障害福祉を専門にしております
きしだ行政書士事務所の情報室です。
今回はグループホーム(共同生活援助)における
厚生労働省令に基づく基本となる指定基準についてまとめました。
グループホーム(共同生活援助)のサービス概要は
主として、夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる
相談・入浴・排せつ・食事の介護その他の日常生活上の援助を行うこと。
これに合わせて居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者について
その日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談等の支援を行うこと
とされています。
今回は主に『介護サービス包括型』(一般的)についてまとめます。
【人員・設備基準の概要】
《人員基準》
従業者
世話人・・・常勤換算
利用者数を6で除した数以上
生活支援員・・・常勤換算
- 障害支援区分3・・・利用者の数を9で除した数
- 〃 4・・・〃 6で除した数
- 〃 5・・・〃 4で除した数
- 〃 6・・・〃 2.5で除した数
サービス管理責任者
- 利用者30人以下1人以上
利用者31人以上1人に利用者数30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た
管理者
- 常勤かつ原則として管理業務に従事すること
ただし支障がない場合は他の職務の兼務可能
《設備基準》
- 住居・・・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との
交流の機会が確保される地域。
入所施設又は病院の敷地外であること
- 設備・・・1以上のユニットを有すること。
ユニットの居室面積・・・収納設備を除き7.43㎡以上(約4.5畳程度)
- 定員・・・事業所の定員:4人以上
住居の定員:2人以上10人以下
ユニットの定員:2人以上10人以下
ユニットの居室の定員:1人
【基本方針】
厚生労働省令からの抜粋
共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
要約しますと
- 地域において利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むこと
- 利用者の状況に応じて日常生活上の援助を行うこと
- 自立した日常生活へ移行するための支援を適切かつ効果的に行うこと
を目的とする
【人員に関する基準】
《世話人》
常勤換算方法で利用者の数を6で除して得た数以上
《生活支援員》
常勤換算方法で利用者の各障害支援区分別に計算が必要です
※世話人及び生活支援員は事業所ごとに利用者の生活サイクルに応じて
一日の活動終了時刻から開始時刻までを基本としています。
夜間及び深夜時間帯以外の時間帯のおける必要な員数を確保するものとする。
夜間及び深夜の時間帯:概ね22時から翌朝5時
《サービス管理責任者》
- 当該事業所の専従ただし支障がないと判断される場合は他の職務と兼務も可能
- 利用者の数は前年度の平均値とする
- 新規に指定を受ける場合は推定数による
《管理者》
- 常勤かつ専従ただし支障がないと判断される場合は
他の職務と兼務も可能
【設備基準】
《立地》
利用者に家庭的な雰囲気のもと、共同生活を送り地域との交流を図ることで
社会との連帯を図ることを目的とする観点から
入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく
住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域
に立地されることを求められています
《共同生活住居内の設備等》
共同生活住居内の設備等は利用者の障害の特性に応じて工夫されたもの
例えば車いす利用者の場合は廊下幅の確保やバリアフリー化など。
《ユニット》
ユニットとは居室及び居室に隣接した相互に交流を図ることができる設備により
一体的に構成される生活単位とされています
住居においては1以上のユニットを設けることとされており
ユニットごとに風呂・トイレ・洗面所・台所等
日常生活を送るうえで必要な設備を設けなければならない
- ユニットの定員:2人以上10人以下
- 1の居室の定員:1人
- 1の居室の面積:7.43㎡以上(和室であれば4.5畳)収納設備は別途確保
- 居室には廊下や居間へつながる出入り口があり他の居室と明確に区分されていること
【運営基準】
《入退去》
- 入居に際して利用申込者の状況等の把握に努めること
- 退去に際して利用者に対し適切な援助を行うこと
- 入退去の記録は受給者証に記録し、市町村に対し報告しなければならない
《利用者負担額等の受領》
- 支給決定障害者から利用者負担額の支払いを受けるものとする
- 支払いを受けた場合は領収書を発行する
- サービス費の支払いに関しあらかじめ同意を得ること
その他利用者から直接支払いを受けることが可能な費用
- 食材料費
- 家賃
- 光熱水費
- 日用品
- 日常生活に要する費用・・・身の回り品・教養娯楽等・送迎費用等
※これらについてもあらかじめ支払いを受けることへの説明・同意を得て
支払いを受けた場合は領収書を発行すること
【サービス管理責任者の責務】
- サービス管理責任者は利用申し込みがあった場合
その申込者が利用している他の障害福祉サービス事業者等に照会し
その利用申込者の心身の状況及び利用状況を把握すること
- 把握したその利用申込者の状況に応じて、自立した日常生活を
営むことができるように定期的に検討し、必要な支援を行う
- 利用者が自立した社会生活を営むことができるように
指定生活介護事業者等との連絡調整を行う
- 他の従業者に対する技術指導及び助言を行う
- 利用者の自己決定の尊重を原則として適切に意思決定支援を行う
【地域との連携】
共同生活援助の事業が地域に開かれた事業として
地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等
地域との交流を図らなければならない
- 利用者及びその家族、地域住民の代表、市町村の担当者等により構成される
地域連携推進会議を概ね年1回以上開催する
- 地域連携推進会議の構成員による見学の機会を概ね年1回以上設ける
- 共同生活援助事業者は上記の記録及び公表をしなければならない
- これらは外部の第三者による評価及びその公表に代えることができる
【介護及び家事】
介護は利用者の心身の状況に応じて適切な技術をもって行う
利用者の人格に十分配慮しなければならない
調理・洗濯その他の家事は利用者と従業者が共同で行うよう努力すること
【社会生活上の便宜の供与】
利用者が充実した日常生活を営めるよう、利用者が通う日中活動サービス等の
事業者との連絡調整や余暇活動等の支援に努めなければならない。
郵便や証明書の交付等について、利用者が必要としている場合は
原則その都度利用者の同意を得て代行しなければならない。
特に金銭に係るものについては、書面等をもって事前に同意を得て
都度事後確認することとする
【運営規定】
事業所の運営に関する重要事項について運営規定を定めなければならない。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務内容
- 入居定員
- 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
- 入居に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
運営規定のサンプルは指定申請をする県・市のホームページ等に載っている場合がありますので確認されるとよいでしょう。
神戸市の場合はこちら神戸市:障害福祉サービス事業等の指定申請(事業者向け)
【勤務体制の確保】
- 世話人・生活支援員及びサービス管理責任者の日々の勤務体制
- 常勤・非常勤の別
- 管理者との兼務関係
これらを明確にしておかなければなりません。
従業者の資質の向上のために、研修の機会の確保も必要とされています。
また適切な指定共同生活援助の提供の観点から、
職場におけるハラスメントの防止対策を講じることが必要です。
上司・同僚に限らず利用者やその家族から受けるものも含まれます。
- 相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
- 被害者への配慮に対する取り組み
- 被害防止のための取組(マニュアル整備等)
【支援体制の確保】
サービス提供体制の確保のため他の関係機関との連携及び支援体制の確保が必要とされています。
また、そのために定員の遵守が必要です。
利用者の急病等に対応するためにあらかじめ協力医療機関を定めておかなければいけません。
この医療機関と事業所との距離は近距離とされており
各指定申請を受ける県や市によって概ねの所要時間が決められていることがありますのでご確認ください。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?
グループホームは利用者が自立した日常生活を送ることができるように
また健常者と同様に娯楽を楽しんだりできるように、利用者自身やそのご家族が
サポートできない場合は事業者にそのサポートが求められます。
そのための取組の基準が決められているためかなり細かい内容となっています。
また運営指導の内容にも、記録があるのか、同意書があるのか、領収書は発行しているのか、都度確認すべき利用者の意思は反映されているのかなどが含まれます。
このような書類がそろっているのか毎月確認して運営指導に備えましょう。
(※運営指導のためではなく適切な運営のためです)
きしだ行政書士事務所では障害福祉事業所の運営サポートを行っております。
お気軽にお問合せください。
お問い合わせはこちらからお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。