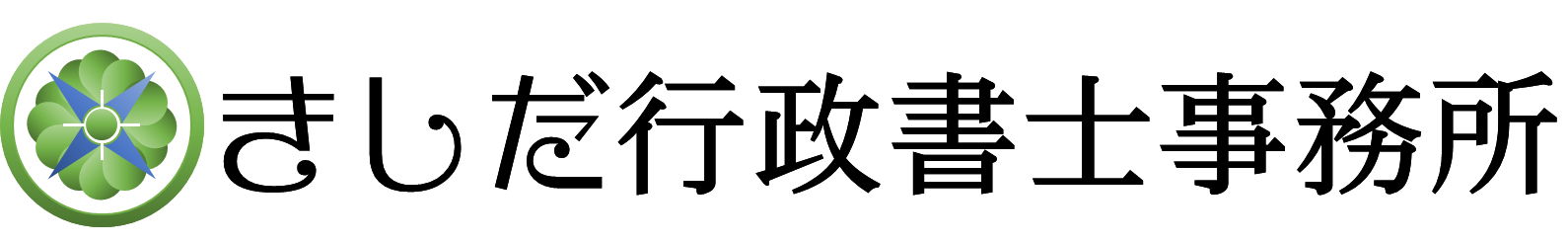【運営指導(共同生活援助)が強化されます~今できることは?】
神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。
今回は運営指導(共同生活援助)について必ず見られるポイントに絞って
まとめました。
2025年度の運営指導について共同生活援助は強化の対象になっています。
運営指導について最近ご相談を受けることが増えてきました。
皆さん一律に「怖い」と感じられている様子です。
ただマイナスなイメージで受け入れるより、今の運営が適切であるのか?
今後長く事業所を運営していくために必要なことを、ご自身の解釈だけでなく
行政とともに見直す良いきっかけにもなり得る機会です。
まずはよく見られるポイント(運営上大切なこと)を見てみましょう。
【主な指摘事項~2024年度集団指導より兵庫県】
2024年度の兵庫県による集団指導の資料からは
以下の3点が指摘事項となっています。
参照:2024年集団指導資料兵庫県1_kyotsu.pdf
①人員に関する基準
・管理者、サビ管の従事実態が確認できない
・業務委託契約書が有効ではない
②運営に関する基準
・身体拘束適正化の取組について
・虐待防止の取組について
・事業所における勤怠の管理
・重要事項説明書の内容
・個別支援計画について
・提供される便宜に要する費用の精算
・消防避難訓練
・非常災害対策
・他の指定障害福祉サービス事業所等との密接な連携について
③介護給付費等の算定及び取り扱い
・法定代理受領の通知
・医療連携体制加算
・夜間支援体制加算
・帰宅時支援加算
・処遇改善加算
となっています。
この中から「減算がある」「必ず見られる」を見ていきましょう。
【虐待防止に関する取り組み】
R4年から義務化となっている虐待防止に関する取り組みについてまとめます。
《運営規程に定めること》
・虐待防止に関する担当者
・成年後見制度の利用支援(指定権者により異なります)
・苦情解決体制の整備・活用
・従業者に対する虐待防止を啓発するための研修実施
・虐待防止委員会の設置・・・年1回以上

✓指針を整備する
✓研修は採用後1か月以内、全従業員対象年1回以上実施
役割を再度見直しましょう
・虐待防止のための計画づくり
・虐待防止のチェックとモニタリング
・虐待発生後の検証と再発防止策の検討
・通報体制の整備
【身体拘束適正化のための取組】
R4年から義務化となっている身体拘束適正化のための取り組みについてまとめます。
参考:厚労省『障害者福祉施設における障害者虐待の防止と対応の手引き』
実施手順
①要件の確認
・切迫性:本人又は他の利用者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高い
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行うこと以外に方法がない
・一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである
⇓
✓個別支援会議で組織として要件の確認をした旨の記録
✓管理者、サビ管、虐待防止責任者が出席している
②利用者、家族への説明と同意
・身体拘束が必要な理由・方法(場所・行為・部位・内容)、拘束時間帯及び時間、特記すべき心身の状況、拘束開始及び解除の予定などについて書面で説明し同意を得る
・個別支援計画に盛り込む
③記録と身体拘束の解除に向けた再検討
・身体拘束を行った場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する
・身体拘束の原因となる状況の分析を行い、定期的に身体拘束解除に向けて、必要性や方法を再検討し記録する
④運営規程に定める
《身体拘束に係る同意を得ておらず突発的に身体拘束等が必要な状況が発生した場合》
①施設長へ連絡する⇒②利用者、家族に口頭で説明し同意を得る⇒③事後速やかに書面で同意を得る(口頭で了解を得た旨の記録)
【個別支援計画】
個別支援計画の作成手順を再確認しておきましょう。
①利用者の基本情報シートを作成
・利用者の基本情報、家族構成、主な生活歴、他の施設の利用状況、施設利用に至った経緯、障害の状況・程度、健康状態
②アセスメント(面接)
・利用者の能力・置かれている環境
・日常生活全般の状況の評価
・利用者の希望する生活や課題を把握する
③原案作成
・自立した生活が送れるよう支援内容を検討。
・利用者や家族の意向
・総合的な支援の方針
・生活全般の質を向上させるための課題
・提供するサービスの目標と達成時期
・サービスを提供するときの留意事項
・加算の前提となる支援内容を位置づけ
・緊急やむを得ない身体拘束が必要な利用者についてはその内容を盛り込む
④個別支援計画の検討会議
・担当者会議をする
議事録を記録、保管する
⑤利用者、家族への説明
・文書による同意
⑥利用者へ交付
・他の福祉サービス支援事業者への交付する
⑦モニタリング
・定期的な面接
・記録する
⇓
②へ戻って③④⑤⑥⑦へ(6か月ごと見直し)

✓共同生活援助における体験利用について個別支援計画を作成していなければ減算の対象です
✓他の障害福祉サービス等との連携のため、作成した個別支援計画書を相談支援の担当者や利用する他のサービス事業所へ交付すること
✓個別支援計画に位置づけが必要な加算の例

【運営規程、重要事項説明書、利用契約書】
運営規程について、事業所において変更届を提出している場合、合わせて運営規程の変更も必要です。事業所の現状(人員配置など)と相違点が無いかを確認しましょう。
そのうえで次に重要事項説明書との齟齬がないか確認してください。
利用契約書について、契約期間が支給決定期間の範囲内ですか?
この確認ができるように、受給者証の支給決定内容が載っている箇所と事業所が記載した箇所のコピーを保管してください。
×契約期間の記載がない
契約書の署名を代筆する場合、欄外に代筆した旨、続柄、氏名を付記します。
×代理人欄ではありません
個人情報提供の同意をもらっていますか?
同意する内容を明確に記載し書面で同意を得るようにしましょう。
《掲示》
・運営規程
・勤務体制
・協力医療機関
・苦情窓口
記事が難しい場合は『閲覧ファイル』として備え付ける
【その他日常生活費の受領】
その他日常生活費は具体的に、「身の回り品」「教養娯楽費」「クラブ活動や行事の材料費」「送迎に係る費用」などです。
これらを受領するのであれば、運営規程に定めます。
・対象となる便宜及びその額
・重要事項説明書への記載も必要
・利用者へあらかじめ便宜の内容及び費用について説明し同意を得ます
・受領した場合は領収書を交付します(その記録も残します)

×お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金⇒あやふやな名目は認められません
※グループホームにおける食材料費については、厚労省より通知が出ています。
『食材用費として徴収した費用は適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴収した食材料費に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、当該事業所の利用者の今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要があること。
また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更時において利用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から求められた場合に適切に説明を行う必要がること。』
求められた場合にいつでも提示できるように適切に管理しましょう。
【避難訓練、非常災害時の訓練】
消防避難訓練を実施する際には、可能な限り消防署の立ち合いを求め、通報や連絡体制の整備の確認をすること。
またそれらの訓練の実施の記録を残し、従業者へ周知します。
非常災害に備えるための訓練について、事業所独自の「業務継続計画」を作成し
想定される災害についての訓練を実施します。

参照:神戸市集団指導サービス共通編
【まとめ】
運営指導は障害福祉サービス事業所が運営の基準に則って
適正に管理・運営されているかを確認するためのものです。
必要に応じて助言や指導が行われますが
実際に運営指導を経験した事業所からは
「利用者さんの為を思って運営されていますね」
とお褒めの言葉をもらいうれしかった。
「運営する上でわからないことを正しく理解する良い機会だった」
「アドバイスをもらえてよかった」等前向きなお声も聞かれます。
事業所を運営する基準を正しく理解し運営していれば怖いものではないと思います。
弊所では事業所の運営サポートやご相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。ご相談は無料です(1時間程度)
ご相談はこちらからお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました