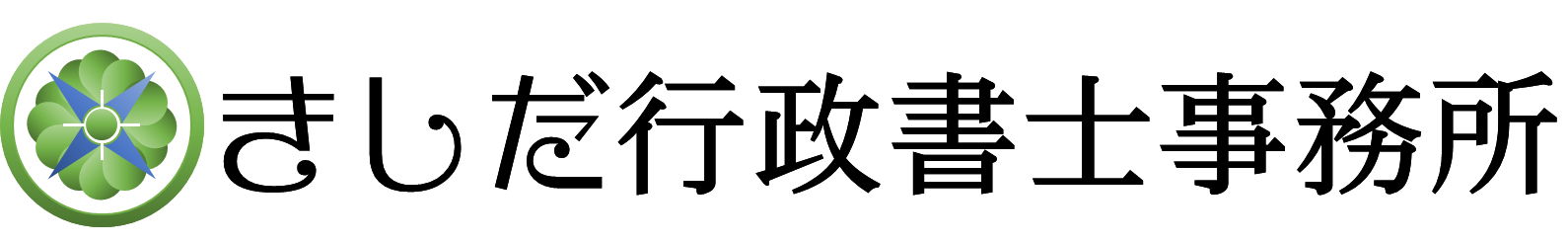【障害児通所支援+障害福祉サービスの多機能型】要件を解説
神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。
少し前にはなりますが、お問合せをいただきました「多機能型事業所」を設立するのに
気になる要件や報酬の算定基準を解説します。
今回は「障害児通所支援」と「障害福祉サービス」との多機能型事業所です。
障害児と障害者のサービスを一体的に行う事業所ということになります。
昔は同じ建物でも異なる出入り口があればよいといった要件になっていたらしいのですが
現在は入口に関する要件はありません。
障害児から障害者へ成長する過程において提供する支援のつながりを求めて
設立を検討されているお客様でした。
特に聞きたい点として「人員配置」と「報酬の算定基準」です。
それでは見ていきましょう。
《多機能事業所の特例》
多機能型事業所にはいくつかの特例があります。
①従業者の員数に関する特例(基準省令第80 条)
従業者(管理者を除く)については、専ら当該職務に従事する必要があるが、多機能 型事業所の場合は、当該多機能型事業所の職務に専従することとし、それぞれの事業の 専従要件までは課さないものとする。
その上で、多機能型事業所として行う指定通所支 援に必要な従業者の員数が確保される必要がある。
②設備に関する特例 サービスの提供に支障のない範囲内において兼用することが可能
③利用定員に関する特例(基準省令第82 条)
・生活介護など指定障害福祉サービス(多機能型が認められている事業)を行う多機能 型の事業所を行う場合、全体の合計で、20人以上であること
・事業所それぞれについて、事業ごとに定める利用定員以上であること
(生活介護・自 立訓練・就労移行支援 6 人、就労継続支援 10 人、児童発達支援・医療型児童発達支 援・放課後等デイサービス5人)
④報酬について
・報酬の算定に当たって、定員規模については、当該多機能型事業所において行う指定 通所支援の利用定員の合計数を利用定員として算定します。
・ただし、加算はサービス毎の定員に応じた定員区分により算定されます。
・ただし多機能型事業所等のうち、上記①従業者の員数等に関する特例によらない多機 能型事業所においては、当該多機能型事業所において行う指定通所支援の利用定員の それぞれの規模により算定されます。
・ただし、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者が兼務する場合にあっては、実施する複数種類の事業の合計の総定員により算定されます。
・ただし、人員配置体制加算は、当該サービス提供単位の定員規模により算定する。
これらの特例をもとに障害児通所支援と生活介護事業所を多機能型で運営する場合の
生活介護事業所における報酬の算定方法や実際どのくらいの報酬になるのか試算してみました。
【生活介護の指定基準】
まずは基本の人員配置について確認していきます。
・管理者・・・次のいずれかを満たす者
(ⅰ)社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
(ⅱ)社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
(ⅳ)社会福祉施設長認定講習会を修了した者
・サビ管・・・利用者数60以下:1人以上
・医師・・・利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導に必要な数
・看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)・・・1人以上(単位ごと)
・理学療法士又は作業療法士
日常生活に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、必要数(単位ごと)
※機能減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士を、機能訓練指導員として理学療法士又は作業療法士に代えて置くことができる。
・生活支援員・・・1人以上(単位ごと)常勤1人以上
○専ら当該事業所又はサービス単位の職務に従事するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
サービス提供職員(看護職員・理学療法士等・生活支援員)の総数(単位ごと(ⅱ)~(ⅳ)の配置総数)
・平均障害支援区分4未満の場合
常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上
・平均障害支援区分4以上5未満の場合
常勤換算方法により、利用者の数を5で除した数以上
・平均障害支援区分5以上の場合
常勤換算方法により、利用者の数を3で除した数以上

例:障害区分6が3人、障害区分5が3人、障害区分4が3人ならば平均障害区分は5
→9÷3=3人(常勤換算)
《設備》
・訓練・作業室は有効面積概ね3㎡/人以上を目安としています
・多目的室は有効面積概ね10㎡以上を目安としています
※相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。
《減算について》
・営業時間が4時間以上6時間未満・・・70/100
4時間未満・・・50/100
・医師の未配置・・・12単位/日 減算
例:12単位×239日=2,868単位×10.73円=30,773円/年
その他・定員超過、人員欠如、個別支援計画未作成、大規模事業所(定員81人以上)、情報未公表、BCP未策定、身体拘束廃止未実施、虐待防止措置未実施
《加算について》
人員配置体制加算、福祉専門職員等配置加算、常勤看護職員配置加算、送迎加算など
《生活介護の介護サービス費》
・利用定員10人以下
・所要時間5時間以上6時間未満
※利用時間5時間未満の利用者が全体の50%以上→70/100になる
区分6・・・1,136単位×3人=3,408単位×239日=814,512単位
区分5・・・849単位×3人=2,547単位×239日=608,733単位
区分4・・・588単位×3人=1,764単位×239日=421,596単位
合計1,844,841単位×10,73=19,795,143円
特例を利用した場合
・利用定員11人以上20人以下
・所要時間はおなじ
区分6・・・904単位×3=2,712単位×239日=648,168単位
区分5・・・676単位×3人=2,028単位×239日=484,692単位
区分4・・・469単位×3人=1,407単位×239日=336,273単位
合計1,469,113単位×10,73=15,763,797円

差額4,031,346円←経費と比較してどのように考えるか?
参考
《人件費》
サビ管30万、看護職員24万、生活支援員28万+176,000→約100万円/月
1,200万円/年
《経費》
家賃、光熱水費、通信費、駐車場、法定福利費、交通費ほか
※サビ管はどこの事業所でも探すのは難しくなっており、参考のサビ管30万円っでは確保は難しいでしょう(個人的意見です)
ここまでは仮の試算額を出してみました。
ここからはほかのご質問で障害児通所支援事業所で算定できる加算解説します。
障害児通所支援事業所でこれは算定できる?
ご質問は4つ(児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて)
①月1回の参観は加算算定可能か?
②訪問して面談、懇談することは加算の算定可能か?
③入学前の小学校との連携は加算算定可能か?
④幼稚園、保育園との連携は加算算定可能か?
回答はこちら
①『子育てサポート加算』
②『家族支援加算』
③『関係機関連携加算』
④『関係機関連携加算』
それぞれの要件を確認しましょう。
①⦅子育てサポート加算⦆
障害児の家族等への支援場面の観察や参加の機会を提供し、相談支援等を行った場合に月4回に限り算定する。
・あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画へ位置づけて計画的に行う
・児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が観察や参加をする
・支援を行う従業者の一方的な指示や報告だけでなく、個別に障害児の状況や支援内容を説明し相談対応を行う
・従業者1人につき5世帯まで
・日時及び内容の要点の記録
②⦅家族支援加算Ⅰ(個別)⦆
障害児の家族等に個別又はグループにより相談援助を行った場合に算定する。
・あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に位置付け計画的に従業者が
- 障害児の居宅へ訪問
- 事業所において対面で
- テレビ電話等を活用して
障害児及びその家族に対し、相談援助を行う。(1)から(3)全体として一日につき1回、1月につき4回を限度として算定する。
※児童発達支援を提供した日以外の日も算定可能
※児童発達支援を提供しない月は算定不可
※相談援助が30分に満たない場合は算定不可
※障害児が同席しない場合も算定可能。ただし効果的な相談援助となるよう努力すること
※突発的な相談援助は算定不可
・日時及び相談内容の要点を記録
②⦅家族支援加算Ⅱ(グループ)⦆
・あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に位置付けし計画に従業者が
- 事業所において対面で
- テレビ電話等を活用して
障害児及びその家族に対し、相談援助を行う。(1)(2)いずれも児童発達支援を提供した日以外の日でも算定可能
※児童発達支援を提供しない月は算定不可
・2人から8人までを1組として行う。
※同一世帯は1と数える
・ペアレントトレーニング等を行う経験や知識を持つ従業者が行う
・相談援助が30分に満たない場合は算定不可
※障害児が同席しない場合も算定可能。ただし効果的な相談援助となるよう努力すること
・日時及び相談内容の要点を記録
※家族支援加算ⅠとⅡは同一の日に実施した場合でも算定可能
③⦅関係機関連携加算Ⅳ⦆
障害児が就学予定の小学校、特別支援学校等との連携を図るため、保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合、1回を限度として算定する。
・障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得て小学校等へ渡す
・相手とのやり取りの内容を記録
④⦅関係機関連携加算Ⅰ⦆
障害児が日々通う幼稚園、保育所、認定こども園等との連携を図るために、情報共有や連絡調整を行った場合に算定する。
・あらかじめ保護者の同意を得て、障害児が日々通う幼稚園等との間で、個別支援計画の作成又は見直しに関する会議を行う。
・会議にとどまらず日常的な連絡調整を行う
・会議の結果や日々の連絡調整を踏まえ、個別支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、個別支援計画を作成及び見直すこと。
・会議または連絡調整を行った場合の出席者、日時、内容の要旨、個別支援計画に反映させるべき内容を記録する
④⦅関係機関連携加算Ⅱ⦆
・あらかじめ保護者の同意を得て、障害児が日々通う幼稚園等との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行う
・会議の開催にとどまらず、日常的に連絡調整を行う
・会議又は連絡調整を行った場合、出席者、日時、内容の要旨を記録する
・会議や連絡調整等を踏まえ、個別支援計画を見直すなど連携した支援の提供

各加算には「同意」や「記録」が要件となっています。
必ず書面に残すようにしましょう
【まとめ】
いかがでしたでしょうか?
これらの要件は神戸市の手引きや報酬算定基準に載っています。
特に報酬算定基準を読み解いていくことに時間がかかります。
そんな時は専門家に相談されるのも一つの手段です。
今回ご質問いただきました事業者様も大変お困りのご様子でした。
きしだ行政書士事務所ではご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
お問い合わせはこちらからお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。