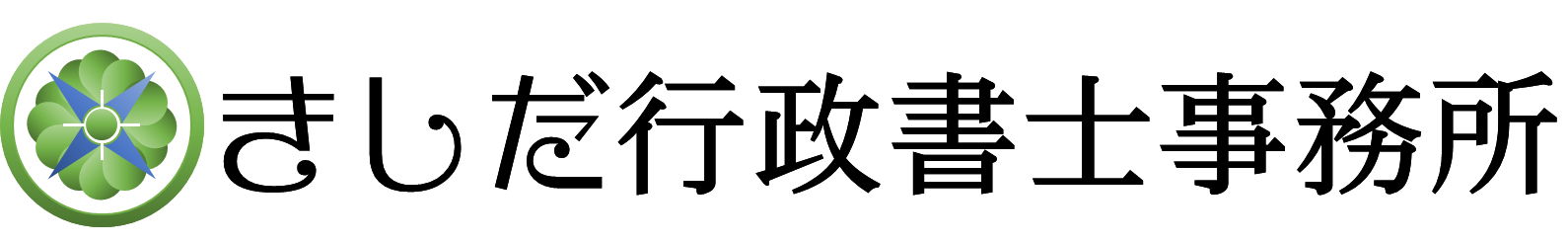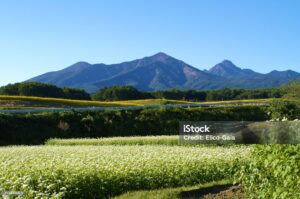【障害福祉サービス:わかりづらい加算をわかりやすく解説】
神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。
今回は先日お客様からご質問をいただきましたわかりづらい加算について
解説いたします。
障害福祉サービスは国が主に厚生労働省の管轄として
基準等を設け発信される資料を基に、事業所は運営することになります。
この厚生労働省が発信する資料、省令等はとにかく読みづらい。
加えて、結局何を言っているのかわからないという文章も多々あります。
一度読んだ経験のある人なら「それそれ。」と言いたくなる者でしょう。
ご相談を受けた事業所様からも「この加算について何度読んでもよくわからん」
というお声をいただきました。
加算について解釈の違いからだとしても、要件を満たさなければ
運営指導後、さかのぼって過誤、返金処理を強いられる場面もあります。
そこで、わかりづらい又複雑な要件の伴う加算について解説します。
【就労継続支援B型・目標工賃達成指導員配置加算】
就労継続支援B型の事業所での人員配置で
目標工賃達成指導員を配置している事業所にとって対象となりうる加算です。
まずは就労継続支援B型の事業所の人員基準についてみてみましょう。
《人員基準》
前年度の平均利用者数に対し
職業指導員・・・常勤換算、10で除した数以上で1人以上
生活支援員・・・ 〃
※1人以上は常勤
サービス管理責任者・・・60人に対し1人以上
※1人は常勤
管理者・・・1人(管理業務に支障がない場合兼務可)
となっています。
職業指導員
就職に必要な知識や技術を身に着けるための
サポートを行う人のことです。
特別な資格は不要ですが、役割を考えると
その事業所の作業内容に応じた知識や経験を持つ人が望ましいところです。
《目標工賃達成指導員配置加算》
- サービス費Ⅰ又はⅣを算定
- 目標工賃達成指導員を常勤換算で1以上配置
- 目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員の総数が
利用者の数を5で除した数以上
- 目標工賃達成指導員が自ら工賃向上計画書を作成
ではその計算はどのようになるのでしょうか?
例:前年度平均利用者数20人、職業指導員+生活支援員の数6:1
20人÷6人=3.3人(小数点第二位切捨て)
目標工賃達成指導員+職業指導員+生活支援員の数5:1
20人÷5=4人
こちらを満たしていれば要件はクリアとなり加算を算定できます。
常勤換算で1人以上ですので、非常勤でも可です。
ただし、職業指導員や生活支援員との兼務はできません。

※工賃向上計画を忘れずに作成しましょう。
《加算されるサービス費》
利用定員20人以下・・・45単位
〃 21人以上40人以下・・・40単位
〃 41人以上60人以下・・・38単位
〃 61人以上80人以下・・・37単位
〃 81人以上・・・36単位
【共同生活援助・人員配置体制加算】
人員配置体制加算とは手厚いサポートができている事業所へ
加算で報酬額をアップさせるためのものです。
令和6年度の報酬改定により基本のサービス費は6:1のみとなりました。
この人員配置体制加算を取ることで令和5年以前に近い報酬額を
受け取ることができるようにしたいですね。
この人員配置体制加算は従来、常勤を週40時間としている事業所と
週32時間としている事業所との間の公平さを取り戻す目的で作られました。
週32時間としている事業所にとっては加配する人員が大きく増えます。
まずは人員基準からみていきましょう。
《人員基準》介護サービス包括型
前年度平均利用者数に対し
世話人・・・常勤換算で利用者を6で除した数以上
生活支援員・・・常勤換算で
- 区分3:利用者数を9で除した数以上
- 区分4:利用者数を6で除した数以上
- 区分5:利用者数を4で除した数以上
- 区分6:利用者数を2.5で除した数以上
※世話人、生活指導員のうち1人以上は常勤
サービス管理責任者・・・利用者数30人以下で1人以上
管理者・・・1人常勤(管理業務に支障がない場合は兼務可)
となっています。
では人員配置体制加算について要件を確認しましょう
《人員配置体制加算》
利用者数に応じ一定数の世話人、生活支援員を加配した場合に算定できます。
この計算方法は『特定従業者数換算方法』で計算します。
特定従業者数換算方法
事業所の常勤時間数ではなく、常に「40時間」で計算します。
常勤時間を週32時間にしている事業所の場合は常勤換算が
かなり減る計算になります。
以下で比較してみます。
《計算方法》
例:利用者9人(区分6が3人、区分5が3人、区分4が3人)、常勤40時間
世話人・・・40時間×(9÷6)人=60時間
生活支援員・・・区分6:40時間×(3÷2.5)=48時間
区分5:40時間×(3÷4)=30時間
区分4:40時間×(3÷6)=20時間
加配すべき世話人等・・・40時間×(9÷12)=30時間
延べ合計188時間←確保すべき時間数
これが常勤32時間の事業所の場合ではどうなるでしょうか?
世話人・・・32時間×(9÷6)=48時間
生活支援員・・・区分6:32時間×(3÷2.5)=38時間
区分5:32時間×(3÷4)=24時間
区分4:32時間×(3÷6)=16時間
加配すべき世話人等・・・188時間-(48+38+24+16)=62時間←加配すべき時間
《加算できるサービス費》
人員配置体制加算Ⅰ(12:1)
区分4以上・・・83単位
区分3以下・・・77単位
【共同生活援助・夜間支援等体制加算】
共同生活援助でほかによく届け出をされる加算に
「夜間支援等体制加算」があります。
こちらは、ややこしくはありませんが要件を満たしているかどうかは
必ず確認してください。
以前の記事に詳しく載せておりますので
こちらをお読みください。
ここでは夜間支援等体制加算Ⅰのみ掲載いたします。
《夜間支援等体制加算Ⅰ》
- 夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、
夜間及び深夜の時間帯(午後10時から翌朝5時までは必ず含む)を通して
必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合
- 一カ所の対象利用者は30人まで
- 常勤、非常勤は問わない
- 委託されたものであっても可
- 夜勤を行う専従の夜間支援従事者を配置
- 共同生活援助計画に位置付け
- 前年度の平均利用者で算定(小数点第1位を四捨五入)
例:前年度の全利用者数の延べ人数1570人、前年度の開所日数365日
1570人÷365日=4.3 四捨五入するため4人で算定
《夜間支援対象利用者2人以下》
- 区分4以上・・・672単位
- 区分3・・・560単位
- 区分2以下・・・448単位
《夜間支援対象利用者3人》
- 区分4以上・・・448単位
- 区分3・・・373単位
- 区分2以下・・・299単位
※夜間支援対象者4人以上は省略いたします

詳しいサービス費はこちらをご覧ください
厚生労働省001205331.pdf
【まとめ】
障害福祉サービスは、国からの給付費により運営をしていく事業です。
税金で賄われているため
各種のサービス費や加算に伴う請求等は
必ずその要件を満たしているのかを確認するようにしましょう。
毎月確認することにより運営指導時に慌てず
必要な書類を準備することができますし、
さかのぼって過誤、返金処理になることを防ぐことにもつながります。
きしだ行政書士事務所では加算等に関するご相談を随時受付しています。
ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらからお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。