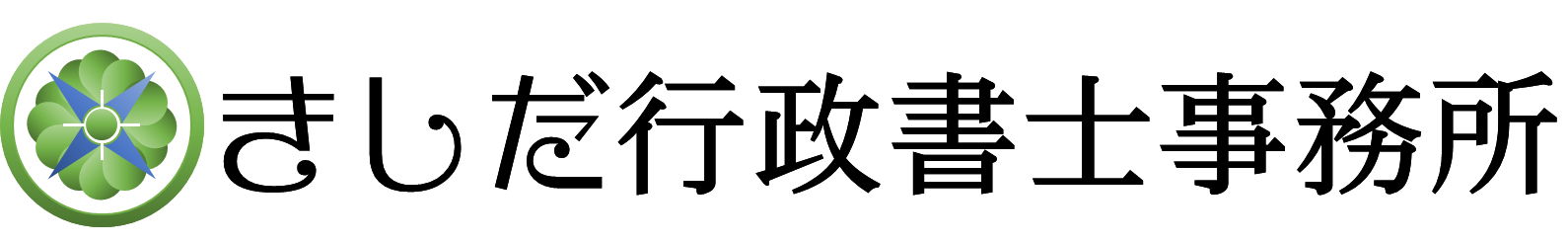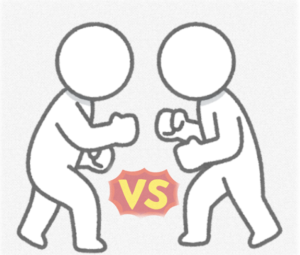【放課後等デイサービスを始めたい人へ】何から準備すれば良い?
神戸三宮で障害福祉専門のきしだ行政書士事務所の情報室です。
今回は、放課後等デイサービスを始めたい人がまず準備することをまとめました。
まず、放課後等デイサービスを始めるためにはその事業所の物件を選びます。
これは一番、難しく各法令や条例等に違反しないことを確認する
つまり放課後等デイサービスをその物件で始めることができるかどうかを
確認することが必要です。
もし物件が見つかりそうなら、賃貸契約や購入を完了する前にご相談ください。
次に、人員の確保です。どの事業所も必要な人員の確保に苦労すると聞きます。
- 児童発達責任者1人以上(常勤・専従)
- 児童指導員又は保育士2人以上(10人まで)1人以上常勤
- 機能訓練担当職員・看護職員(必要な場合)
『物件と人員の確保』とにかくこの2点は初めにクリアすべきです。
そして指定申請の書類をそろえていきます。
たくさんありますので専門家に相談するか、ご自身で行政窓口に聞きながら整えていくかです。
行政のHPに書類の一覧が載っていますのでご確認ください。
神戸市ですとこちらです。神戸市:障害児支援事業の指定申請(事業者向け)
次に「その後の準備」に入ります。
幼稚園、大学を除く障害のある就学児童が対象となるサービスですので
多くの運営基準があります。
【指定申請の書類以外に準備が必要なもの】
- 金銭の受領に必要な書類
- 利用申し込みの際に必要な書類
- サービス提供時の記録
- 給付費の通知
- 個別支援計画の作成(開業後)
- 業務継続計画
- 安全計画の策定
- 衛生管理、感染症対策
- 身体拘束等の禁止のための準備
- 虐待防止のための対策
- 秘密保持
- 苦情解決のための措置
- 事故発生時の対策
1つずつ見ていきましょう。
【利用者負担額の受領】
利用者から事業所はその利用者の負担額の支払いを受けます。
その他にも日常生活において必要となる費用を受け取ることができます。
その他日常生活において必要となる費用
- 食事の費用
- 日用品の費用
- 身の回り品やクラブ活動等の費用
この場合、利用者の保護者に対しあらかじめその内容及び費用について説明し
同意を得なければなりません。そして支払いを受けた後は領収書を交付します。
その他、何らかの理由で金銭の受領を行うときには必ず
- 金銭の使途
- その金額
- 費用がかかった理由
を書面で提示して説明し、同意を得るものとします。
【事業所のサービス内容及び手続の説明】
利用申込者に対し、事業所のサービス内容などがわかりやすく載っている
パンフレット等を活用しながら丁寧に説明します。
そして、重要事項説明書を交付し同意を得ます。
重要事項説明書
- 運営規程の概要
- 従業員の勤務体制
- 第三者評価の実施状況等
同意を得られれば、利用契約書を交付します。
利用契約書には
利用契約書
- 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
- 提供するサービス内容
- 保護者が支払うべき額
- サービス提供開始年月日
- 苦情受付の窓口に関する事項
を記載します。ここに「個人情報提供の同意」も併せてもらっておくとよいです。
他の事業所にも通われている、障害児から障害者として事業所へ通い出すときなど
他の事業所と情報を共有する場合も出てきます。
【サービス提供の記録】
事業所はサービスを提供した場合は、サービス提供記録を都度
記録しなければなりません。(5年保存)
そして、その記録を保護者に確認してもらわなければいけません。
運営の基準には「都度」と記載がありますので原則、利用日毎と解釈します。

指定権者によって扱いに違いがあるようですので
確認してください。
【サービス給付費の通知】
事業所は法定代理受領によりサービス費の支給を受けた場合は、
利用者の保護者に対しその給付費の額を通知し、サービス提供証明書を交付
しなければなりません。
【個別支援計画の作成】
放課後等デイサービス計画を個々の障害児に作成します。(5年保存)
利用開始から約1か月の間に作成が必要と考えるとよいでしょう。
作成に当たりまずはアセスメントです。これは障害児及びその保護者との面談
により行います。これをもとに原案を作成します。
次に原案をもとに担当者会議を開催します。これは個別支援会議でその事業所の
当該障害児にかかわる人すべてが参加するのが望ましいです。
意見を出し合い検討し個別支援計画を作成します。
これを障害児とその保護者に説明し同意を得て交付します。
その後モニタリングをしながら解決すべき課題を把握します。
6か月に1度以上の頻度で計画の見直しを行います。
見直しを行う時には担当者会議→説明・同意・交付→モニタリングを繰り返します。
モニタリングには記録も必要です。

この1連の流れは事業所に定期的に行われる運営指導においても
必ず見られますのでよく理解し不安があれば指定権者に確認するとよいでしょう。
【運営規程】
運営規定は指定申請の時に必要ですが
運営が始まると変更する点も出てきます。
変更しますと、重要事項説明書の変更も利用契約書の変更も必要となります。
ここを忘れてしまう事業所もありますので注意してください。
【業務継続計画】
感染症や非常災害発生時に利用者に対する支援を継続的に実施するため
早期に事業所の再開を図るための計画を策定しなければなりません。
とはいえ、非常災害時には事業所のスタッフも被災者ですので
無理なく可能な限りの早期再開に向けた計画であってほしいと思います。
感染症
- 平時からの備え
- 初動体制
- 感染拡大防止体制の確立
非常災害
- 平常時の対応
- 緊急時の対応
- 他施設及び地域との連携
これらをもとに研修(年1回以上)を行い、訓練(シミュレーション年1回以上)で
計画の確認を実施します。必要に応じて計画の変更も行います。
この研修や訓練の実施については記録を残しておきましょう。
【安全計画の策定】
事業所の設備の安全点検や事業所外で行う活動等の安全対策、
生活上の安全対策を講じなければなりません。
「緊急時の対応マニュアル」「防犯マニュアル」等を作り
従業者へ周知し、研修や訓練を実施します。記録も残しておきましょう。
【衛生管理】
感染症対策委員会を3か月に1回以上開催し、従業者へ対策を周知します
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の策定
感染症対策のための研修の実施を年2回以上開催し記録を残します
感染症が発生した事態を想定し訓練を年2回以上実施します
【身体拘束等の禁止】
障害児の生命又は身体を保護する目的以外の身体拘束は禁止されています。
緊急やむを得ず身体拘束を行うときは、その態様及び時間、その障害児の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要事項を
記録に残さなければなりません。
この記録用紙は必ずすぐに使用できるように作成しておきます。
緊急やむを得ない理由とは
切迫性・非代替性・一時性の3つの要件がすべてそろわなければなりません。
そして組織としてそれらの要件の確認の手続を行ったことを
記録しなければなりません。
身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し従業者へ周知させます。(年1回)
委員会における検討の内容について記録します。(5年保存)
身体拘束等の適正化のための指針を策定します
従業者の研修の実施(年1回以上)。記録も残しましょう。
【虐待等の禁止】
事業者は障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはなりません。
虐待防止のための計画を作成し、虐待が起こりやすい職場環境であるか
モニタリングを実施します。
万が一虐待の発生を確認した場合は再発防止策を検討します。
虐待防止委員会を設置(年1回以上)し委員会の内容を周知させる
虐待防止のための指針の策定
事業所において虐待防止のための研修を実施する(年1回以上)
研修内容についても記録する
虐待防止のための担当者を配置する(児童発達支援管理責任者等)

※「身体拘束適正化検討委員会」と「虐待防止委員会」とは一体的に設置・
運営しても差し支えないとされています。
【秘密保持について】
事業所の管理者や従業者は仕事上知り得た利用者の秘密を漏らしてはいけません。
利用者の秘密を洩らさないよう必要な措置を講じることとされていますので
雇用契約書等に明記するまたは誓約書にサインをもらっておくことが
必要な措置として考えられます。
【苦情解決のための措置】
事業所は利用者の家族や近隣住民の方等からの苦情を受け付けるための窓口を
設置しなければなりません。
苦情受付の担当者、連絡先等を掲示等により周知し
苦情を受け付けた場合には記録をとり、サービスの質の向上を図る取組を
行うべきとされています。(5年保存)
【事故発生時の記録】
事業所は支援の提供時に事故が発生した場合は、速やかに都道府県・市町村・
保護者等へ連絡しなければならないのと同時に
事故の状況・事故に対する処置等を記録しなければなりません。
あらかじめ記録できるよう書式を準備しましょう。(5年保存)
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。
指定申請に必要な書類以外にも開業前にそろえておきたい書式
運営基準に則った指針の作成
運営が始まってからすぐに必要な記録等
準備すべき書類等様々あります。
これらを備えておかなければ、開業して1年以内に行われる運営指導
その後も定期的に行われますがきちんと管理されているかをみられるポイントです。
日々の運営において手間はかかっても運営基準に沿って記録等を行うことで
いつ運営指導のお知らせを受け取っても大丈夫になります。
きしだ行政書士事務所では運営のサポートもさせていただきます。
ご相談は無料です。
こちらからご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。